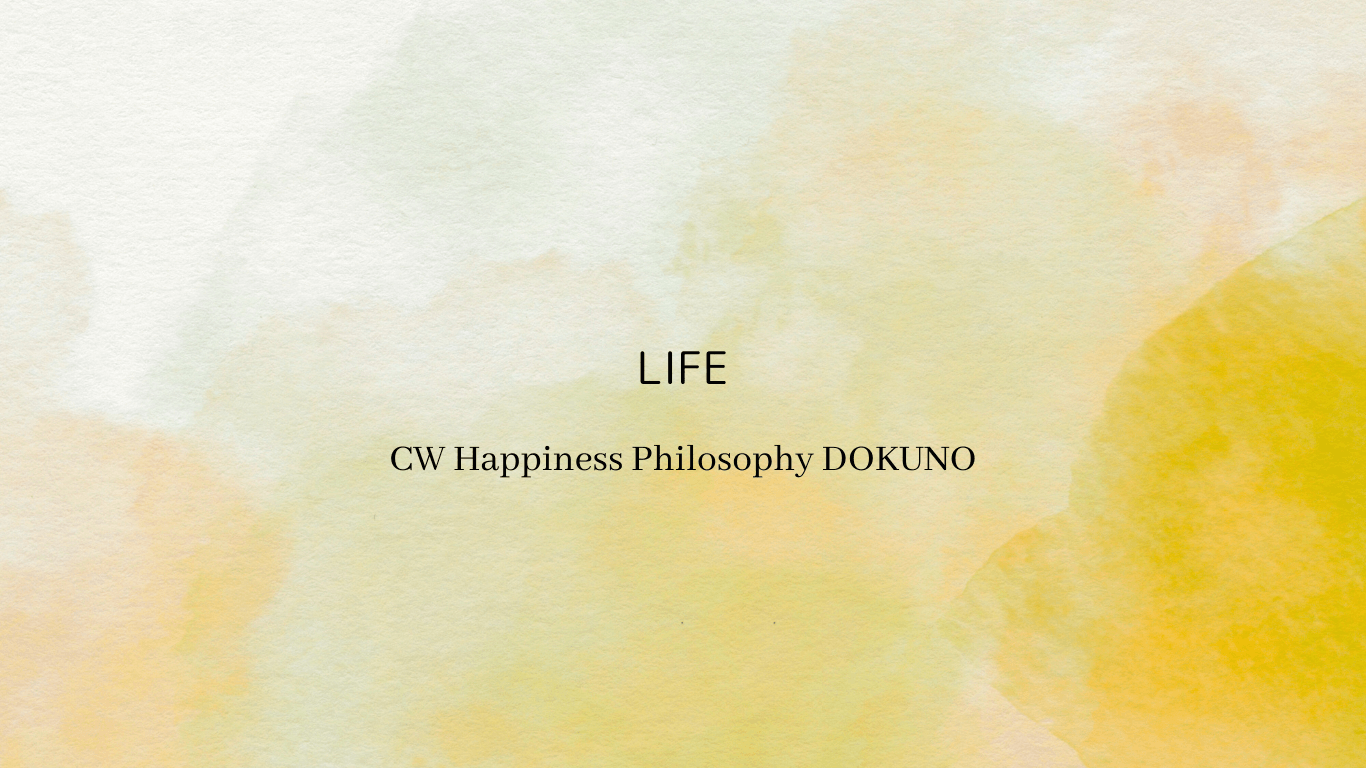「読脳」とは、人の意識できる記憶だけでなく、その人自身も認識していない深いレベルの情報を読み解く独自の技術であり哲学です。
この探求は、「人の役に立ちたい」「人間とは何か?生きるとは何か?」という根源的な問いから始まりました。
読脳開発者 伊東聖鎬は、求めている人に役に立ちたいという一念から様々な方法を試みる中で、約50年前に「キネシオロジー」と出会います。ここで得た「その人の中に、その人の情報を知る術がある」という確信が、読脳の大きな転機となりました。
当初は筋肉を研究の通り道としていましたが、筋肉が行う側の意思によってコントロール可能であることから、やがて術者が「一切コントロールできないもの」の中に、その人を知る術があるという方向へと思考が深まっていきます。
記憶を超えて存在する「人生の情報」の深層
読脳が焦点を当てるのは、現在の医学が扱うような肉体的な情報だけではありません。
人の過去、人間関係、家族の問題、経験、環境、哲学といった、目には見えない情報が、時間と共に消えることなく、その人の中に深く残っているという考えが基盤にあります。
多くの人が「脳に残っている情報」としてまとめることもありますが、読脳では、本人が記憶しておらず「ない」と断言する情報までもが、実際に存在し、読み解かれるのです。
これは、単なる記憶の読み取りではなく、人間の深層に刻まれた、より本質的な情報へのアクセスを意味します。
苦しい体験が「共感」という理解の深さに生きる
伊東聖鎬は、自身の身体的な苦痛(肩の痛みや帯状疱疹など)も「ものすごく価値がある体験」と捉えています。
それは、これらの苦しみを経験することで、「生きることと闘っている」という実感を持ち、克服しようと向き合うことで、同じような状況にいる人々の気持ちを深く理解できるようになるからです。
このような体験の積み重ねにより、通常の医療従事者や家族ですら気づかない、追い詰められた人々の心理状態や背景を「想像できる」力が育まれていきます。
相手の人生を深く聴き、また様々なカテゴリーのたくさんの人の人生と向かい合っていくことで、人生を捉える力が層を増し、通常では出てこないような情報が「読脳のセンサー」を通して引き出されるのです。
人類を繋ぐ「元と繋がるライン」と「愛」の哲学
読脳が読み解く情報の根源には、記憶に残らない、しかし確かに存在する「元と繋がるライン」というものが関係しています。これは、DNAや血縁を超えた、ホモサピエンスとしての共通のネットワーク、つまり「愛」であると表現されています。
伊東聖鎬は、「人類愛」とも呼べる、人に対する深い「愛」を前提に生きてきたことが、この「元と繋がるライン」に繋がり、自身の「黄金に光り輝く空間」という特別な経験を通じて、脳の情報と統合されたと述べています。
この「愛」と「ゆらぎ」のラインこそが、人々を深く理解し、読み解くための重要な要素なのです。
「読脳」のメカニズム:センサーが捉える情報
読脳は、脳に残る情報と「元と繋がるライン」の両方に「問いかけ」を行うことで機能します。この問いかけに対し、「センサー」が反応し、その人の持つ真の情報が引き出されるのです。
これは、単に質問を投げかけるだけでなく、相手の人生の軌跡を注意深く聞き、自身の豊富な経験と照らし合わせることで、本人が意識していない、あるいは忘れているような深層の情報を引き出すというプロセスです。
それによって、その人が抱える真の問題の根源を特定し、理解、解決へと導いていくことができるのです。
「読脳」が示す、人と繋がる新たな可能性
「読脳」は、表面的な情報や記憶だけにとどまらず、人の奥底に秘められた「人生の情報」を読み解く画期的なアプローチです。
自身の苦しい体験を乗り越えた共感力、そして人類愛という哲学 に基づいたこの技術は、私たちが互いをより深く理解し、真に「人の役に立ちたい」と願う心を具現化したものと言えるでしょう。
この「読脳」の概念は、私たちがまだ知り得ない人類の深いつながりや、心身の健康、そして生きることの意味について、新たな視点を提供してくれます。